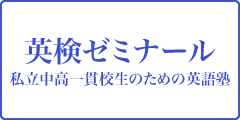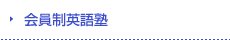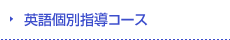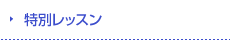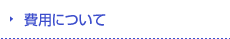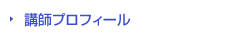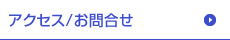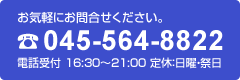Category
Archive

日常の中の外国語(4)
日常の中の外国語(4)
旦那(だんな)<サンスクリット語
「旦那」という単語は、サンスクリット語のdana(ダーナ)の音写であり、その意味は「施し、布施」である。元の意味は「与えること」。
仏教的な脈絡で、寺院や僧侶に財物を施し、経済的支援をする信者のことを意味したらしい。それが時代とともに意味の推移があり、現代の意味に至る。
古代インドの言語であるサンスクリット語は、ラテン語やギリシャ語と同系列の言語であり、これにより民族的に、また文化的にインドとヨーロッパが繋がる。
◯「与える」という単語
サンスクリット語dana
ラテン語donare
フランス語donner
イタリア語donare
※それぞれ上記の単語の形は以下。
サンスクリット語dana=[語根+ana(接尾辞)]。
ラテン語、フランス語、イタリア語は、それぞれ不定詞。
日本語の「ドナー」は英語donorのカタカナ版であり、その語源はラテン語のdonator「贈与者」である。「旦那」という言葉は、臓器提供の「ドナー」という単語と言語的に親戚ということにはなるが、語源的解釈には注意が必要である。
とある岩波新書の本(「朝日新聞の折々のことば」)の中で、「「檀那」はサンスクリット語のダーナが語源。それがラテン語のドーヌム(贈り物)となり…」という記述があった。ここに語源的解釈の混乱が見られる。サンスクリット語「ダーナ」がラテン語の「ドーヌム」に直接なったわけではない。
単に関連しているという脈絡では「旦那」は「ドナー」や「データ<与えられたもの」などの単語と語源的なつながりがある、とは言える。
1786年、英国のサンスクリット語学者が言語学史上、有名な講演を行う。彼の名はウィリアム・ジョーンズ。
彼はこの講演の中で、インドのサンスクリット語とラテン語、ギリシャ語が似ているのは偶然の一致ではなく共通の源から発したことを説いた。
たとえば「父」を表す単語は、それぞれ以下のようになる。
サンスクリット語pitar
ラテン語pater
ギリシャ語patēr
※上記は全てローマ字で表記しているので簡単だが、実際には全て書かれている文字は異なるので、その文字が読めないなら共通性の発見はできない。
ウィリアムは、このような単語の共通性を見抜き、インドからヨーロッパに広がるそれぞれバラバラの言語は、元は一つの言語から派生しているのではないか、という考えに至る。
つまり、かつては一つの民族であった人々が移動により分散されていき、行き着いた地で各言語がさらに独自の発展を遂げていったことになる。
このインドからヨーロッパに広がる言葉の元となる言語は、それ自体が発見されたわけではなく、後に比較言語学の手法により想定され再構成された言語であり、それを印欧祖語と呼ぶ。
この想定言語である印欧祖語からサンスクリット語やラテン語やギリシャ語が派生していく。
「与える」の意味の元の想定言語(印欧祖語)の単語Xがあり、それから時が経ち、なんらかの理由で民族の移動がある。人々が行き着いた地で、それぞれの言語が独自発展を遂げる。
その結果、「与える」の意味の単語が、サンスクリット語の「da(ダー)」、ラテン語「do(ドー)」、「ギリシャ語didomi (ディドーミ)と派生していく。
※表記したサンスクリット語の形は、語根。ラテン語とギリシャ語は一人称単数現在形。
比較言語学が誕生すると、さらに比較神話学が誕生する。神話に詳しい方は、お気づきのように世界には似たような神話がたくさんある。これは一つのものから派生したという単純なものではなく、さらに心理学とも関連してくる。
次回「うちのだんなは〜」と言ってみる時、上記の歴史的背景をチラッと考えてみると、そこの敬意の気持ちが加わってくるかもしれない。
« 前のページ 次のページ »