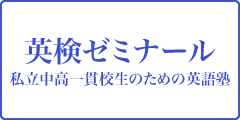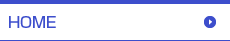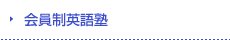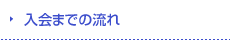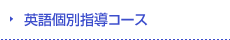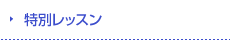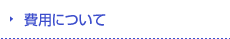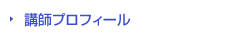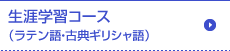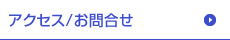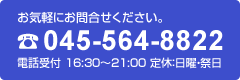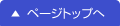Category
Archive
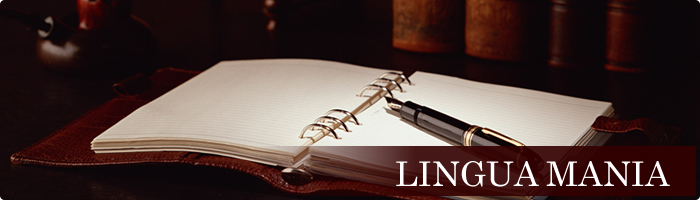
英単語の作り方:特別編 No.7 「学校」の起源
英単語の作り方:特別編 No.7 「学校」の起源
今回のパンデミックにより、世界中の国で学校の休校措置が取られている。そもそも「学校」とは何か?
「働く」とは?「生きる」とは何んぞやというところまで人々の思いはシフトしてくるであろう。グローバル化社会は一旦停止して、各国が引きこもり社会になるかもしれない。
休校中に世界中の人間が「学校」のことを考えています。「勉強だけならネットでよくね?」「勉強は、したい人だけがやればよい、俺は一日中寝てたい」「ずーっとゲームできるし、休校最高!」「やっぱ学校行きたーい!」
学校不要論まで上がってきている。本当に不要なのかどうかは各自が考えることにし、ここでは「学校」「スクール」の起源に迫ってみよう。
「学校」の起源
学校とか勉強とかいう言葉にはどこか強制的な匂いが漂い、直ちに嫌悪感を感じる人もいるであろう。この「学校」を表すschoolの語源はギリシャ語のscholeであり、意味は「暇」であった。
いわゆる勉強、学問は暇を持て余した人々が自由な時間を使って、集い、議論などを行っていたことに端を発すると云う。労働つまり仕事は奴隷が行う。
このことから、もし自分の意志ではなく学ぶことを強いられたら、逆説的にそれはもはや奴隷である、と主張する人もいそうではあるが、実際にはどうだったのだろう。
『西洋古典学事典』(松原國師著、京都大学学術出版会)によると、プラトンの学校アカデ―メイアでは、「笑うことは許されず、また魂の浄化のために小時間の睡眠や肉食の禁断が要求された」らしい。これなどは、どこかカルト宗教臭さえ漂う。
よく耳にする名称の「~アカデミー」は、もちろんこのプラトンの学園アカデ―メイアに源がある。前387年頃に設立されたこの学園の名称アカデ―メイアは、アッティカの伝説上の英雄アカデーモスに由来するらしい。
アカデ―メイアでは、先生と生徒は一つの生活共同体で結ばれ、授業料はなかったらしい。この学園からは、アリストテレスをはじめ、多数の逸材が輩出された。
アリストテレスは、前335年にアテーナイ郊外に学校を作る。その名はリュケイオン。こちらの名称は日本では、ほとんど知られていない。
しかしながら、フランス語を学ばれた方には、なじみ深いlycee(リセ)という言葉がある。ちょうど日本の高校に当たる。このリセの語源になるのがリュケイオンである。
ラテン語では「学校」のことをludusという。ludusを羅和辞典で引くと、「遊戯;競技;学校」などの意味が見られる。
この単語の動詞 ludoは「遊ぶ」の意味になる。やはり勉強に一番大切なのは遊び心であろう。ここまでの考察によると、ギリシャ・ローマに「学校」の源があるように思えるが、事態はそう単純ではない。
ギリシャ・ローマ文明の前には、メソポタミア文明がある。『歴史はスメールに始まる(N・クレマー)』(新潮社)によると、「スメールの学校制度が十分に発達し栄えたのは、紀元前三千年紀の後半である」そうである。
「スメール」という表記に一言。私が所有しているこの翻訳は、私が生まれる遥か昔の昭和34年に発行されたものである。現在では、ほぼ「シュメール」という表現に統一されている。従って、ここでも以後「シュメール」の表記を使う。
シュメールの学校は、役所や神殿、宮殿などで働く人、いわゆる「書記」を養成するための職業的な訓練所であったのであろう。
誰もが教育を受けられたわけではなく、富裕階級の子弟だけが学校に通った。また、学校は男性だけで成り立っていた。
神学、植物学、動物学、鉱物学、地理学、数学、文法などなど、様々な学問が発展していった。専門の教師も存在していたらしく、現在と変わらず安月給で苦労していたらしい。
一方で、教師は生徒を訓育のため鞭打った。生徒は毎日朝早くから太陽の沈むまで学校で学んだ。
メソポタミアで発掘された粘土板には、様々な内容のものがあるが、非常に人間的なものも少なくない。そこには教師と生徒の日常的なやりとりなども伺い知ることができるものもあるようである。
以下は、メソポタミアで発見された粘土板の資料に基づいた私の勝手な想像。たしかに会話の細かい箇所は想像ですが、内容は変えていません。
「君は、なぜ遅刻したのかね?」
「すいません、もう二度としません!」
「君は、先週もそう言っていたね!」
「先週は、母が起こしてくれなかったのです。」
「君は、自分の遅刻を人のせいにするのかね?お尻をだしなさい!鞭打ちです!」ビシッ!!
この生徒は先生の怒りを鎮めるために、家に帰ると父にこう言う。
「父さん、先生を家にお招きしたいのですが。」
「どうしたのだ?」
「いえ、尊敬する先生に敬意を示しておく必要はありませんか?」
「その通りだ。お招きしよう!」
父親は、先生に葡萄酒を飲ませ、おいしいものを食べさせる。衣服を与え、指輪を贈る。 つい先ほどまで怒り狂っていた先生は、少し機嫌が良くなるのである。
「おたくの息子さんは、優秀ですね!努力家です!将来は立派な書記になるに違いありません!でも、遅刻はいけませんよ(笑)」
今から約5,000年前の日常である。
« 前のページ 次のページ »