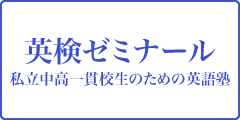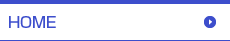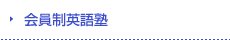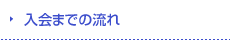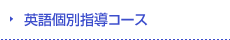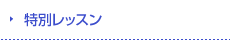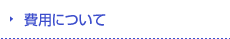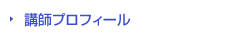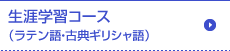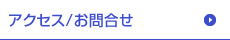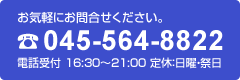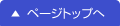Category
Archive
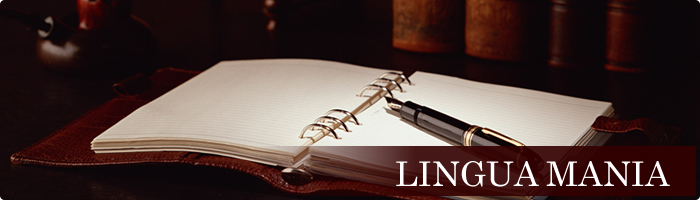
英語学習の方法論
英語学習の方法論
「愚直な練習」と「目的のある練習」
語学学習と音楽の習得はよく似ていると言われている。1日の練習量がモノを言う。しかしながら、ここに大きな問題も含まれている。
最近の心理学や神経生理学の研究によって、ちょっと前まで謎だったことが少しずつ明らかにされつつある。
よく生徒から受ける質問に「1日何時間くらい勉強したら良いですか?」というのがある。
ダラダラ勉強することは、やらないよりは良いのかもしれないが、あまり意味がない。
では、どうしたら良いのか?
「目的のある練習」をすることが効果的であることがデータによって示されている。この練習法の対極にあるのが「愚直な練習」である。
目標は才能を引き出すだけでなく、才能を創り出すことが研究によって分かってきている。
例えば、ピアノの練習を1日1時間実行しているAさんとBさん。
Aさんは、ただ1時間とにかく練習する。ただ曲を弾いて時間のノルマをこなす。
一方のBさんは、「課題曲を適切なスピードでミスなく最初から最後まで3回連続で弾けること」を目標にしている。
誰でも直感でBさんの上達がより早いことは感じとるだろうが、そのような実験データは既に存在している。トレーニング法とその結果に関する研究は実はかなり進んでいる。
時間をかければ人は物事を上達させることができるのだろうか?
運転歴30年のドライバーは運転歴5年の人より上手いのだろうか?
データが示す通り、そのような結果にはならない。
それが何であれ、人が技術を習得する際、ある段階(それが許容できるレベル)に到達すると、そこから先は、全く向上しなくなってしまうことがデータに示されている。
もっと卑近な例を一つ。30年やっているレストランの味は開店3年のレストランの味より格段に上なのだろうか?私たちの経験値が直ちに「ノー」と言わせるであろう。
改善に向けた意識的なトレーニングをしないとむしろ劣化が始まる。コンフォートゾーン(居心地の良い領域)に人は留まる傾向がある。
「コンフォートゾーン」とは「まあまあ無難にできれば良いと感じる領域」と考えておけば良い。
「目的のある練習」の実践
私たちは「愚直な練習」ではなく「目的のある練習」を行なっていこう。本当はまだまだありますが、とりあえず簡単に1〜10でまとめました。残りは教室にて、一人ひとりにお伝えします。
1 小さな目標を決めて、それを完璧にこなす。はっきり定義された具体的目標を持つことが大切。
2 さらに、もう一つの小さな目的を設定して、完璧を目指す。ダラダラしない、集中して行う。
3 「小さな完璧」の積み重ねは自信につながることを実感する。「小さな完璧」+「小さな完璧」=「少し大きくなった小さな完璧」
4 「愚直な練習」=ダラダラ勉強することは、不安が増幅する。寝る前に今日は何を勉強したかを具体的に思い出してみるとよい。おらく何も思い出せないでだろう。「やった感」だけで中味がないから、不安が残る。→集中と具体的目標をもつようにする。
5 フィードバックが必要。
その方法が正しいものかどうか、また実力向上につながっているかどうかを自分以外の人に見てもらう必要がある。試験もフィードバックと考えられる。
6 コンフォートゾーン(居心地の良い領域)から飛び出すことが必要。
それまでできなかったことに敢えて挑戦する。楽な勉強ばかりしないようにする。
7 壁を乗り越えるために別の方法を試す。
一つの方法でダメなら別の方法を探そう。必ず道は見つかる。行き詰まった時に「もっとがんばる」ではなく、「別の方法を試す」ことを実践してみよう。
8 記憶やトレーニングに負荷をかける。
当教室で準2以上の人に英語リスニングを2倍のスピード聞くというトレーニングを課しています。これは高地トレーニングのようなものです。自宅でも毎日やれば確実にリスニング能力は向上する。
9 リスニング力を向上させるためには自分が正しい発音のトレーニングを実践する必要がある。
自己流で発音していると変なクセが染み付いて取れなくなるので危険。必ずモデルスピーチを聞いた後に発音練習しよう。
10 何のための文法なのかを意識化する。
問題の答えが1だと2だとか、当たったハズレたはどうでもよい。大切なのは、その文法を知ることで得られるメリットを感じとること。
« 前のページ 次のページ »