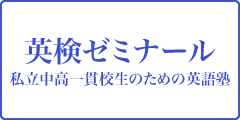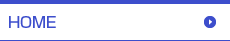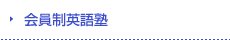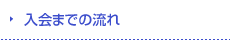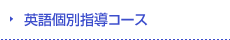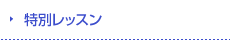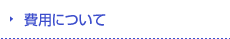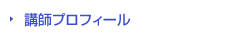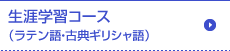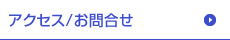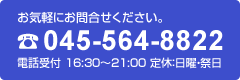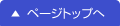Category
Archive
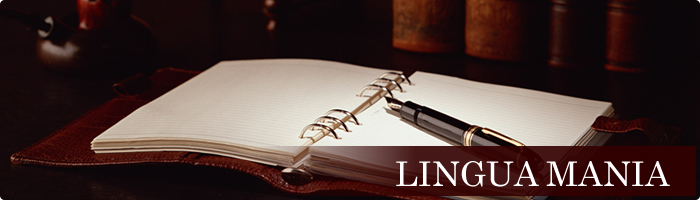
犠牲とは何か?
犠牲とは何か?
たとえば「犠牲」という漢字を凝視すると、そこには牛や羊がいることが見て取れ、なるほど古代の中国においては牛や羊が犠牲獣として神に捧げられていたのだなという大雑把な推測が成り立つ。
古代のギリシアやローマでも同様に「牛」や「羊」のような生きた動物が神に捧げられていた。神話・伝説によれば、時には生きている人間も。人身御供。
古代ギリシアのアテーナイは、その昔、クレタ島のミノス王に牛耳られていた。ミノス王の妻は怪物ミノタウロスを産んでおり、これは迷宮に閉じ込められていて、毎年、アテーナイから七人の少年と七人の少女がミノタウロスに生贄として捧げられていた。
この現状を打破するためアテーナイのアイゲウス王の息子テーセウスは怪物退治に乗り出す。そこにミノス王の娘アリアドネが助け舟を出す。彼女はテーセウスに恋してしまい、怪物退治の後に一緒にアテーナイに逃げたいと言う。そこで彼にミノタウロスを殺すための剣と迷宮からの脱出のための糸を手渡す。…..
続きは「ギリシア・ローマ神話」を読んでみよう。
さて、私たちの牛と羊に戻ろう。「犠牲」という漢字から牛と羊という特定の動物を推論したのだった。神話や伝説の情報から当て水量すると、古代においては、動物ではなく人間が生贄として宗教的に捧げられていた可能性があるということも見た。
神に捧げるものとして、英語ではvictimとofferingがある。victimは「犠牲」、「生贄」であり、これはラテン語のvictima 「犠牲獣」が語源である。
一方のofferingは、「供物」であり、それは「農作物」であったり、「お酒」であったり、「花」であったりする。
「犠牲、生贄」を意味するsacrificeという英単語もあるが、これは語源分析的には、「聖なる行い」を意味する。
供儀として捧げられるものは、時代とともに変化していて、より軟弱傾向にあると言えるであろう。
人間→牛や羊→農作物、お酒
現代では私たちは「お花」をお供えものとして捧げている。さらに「祈り」や「念仏」などの「言葉」を捧げるというのは、かなり最近のことなのではないだろうか?
人間→牛や羊→農作物、お酒→お花→言葉(お祈り、念仏)
捧げ物の最終段階である「言葉」は、かつては「神聖なもの」であったけれど、最近では言葉は単なる道具であるなどと扱われて虐げられている。しかしながら私たちは気をつけなければならない。
フランスの詩人ジャン・コクトーはかつてこんなことを言っていた。「言葉は魂の乗り物である」と。
心のこもっていない言葉は、相手に直ぐにそれと分かってしまう。私たちが日々テレビで目にする「死んだ魚の目をした腹話術の人形」のような人が話す言葉を聞けば、そこにはもはや人間が入っていないことは残念ながら誰もが感じてしまう。
« 前のページ 次のページ »