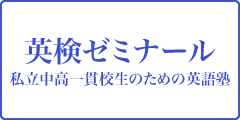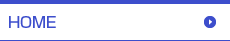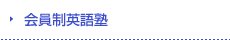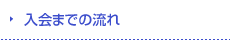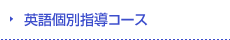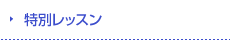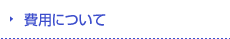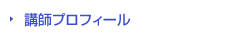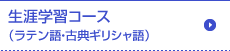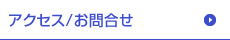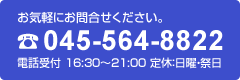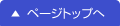Category
Archive
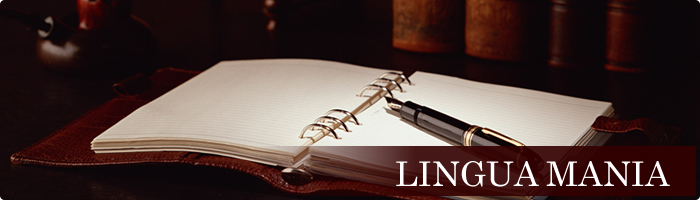
日常の中のラテン語(1)
日常の中のラテン語(1)
たとえば、Mr. という英単語があり、なぜピリオドが付いているのかと質問されたら長い単語を縮めた場合、つまりMisterを初めの文字(M)と最後の文字(r)、さらにピリオド(. )で表記することができると答えることになるであろう。
2、3の例も忘れずにつけ加えよう。
Dr.はdoctorであり、発音が異なるので注意が必要だがMrs.はMistressの短縮形であり、極め付けは最もよく使われる英単語の記号No.(ナンバー)はnumberであり….これは理論的にNr. になるはずであるが…..
注)Ms.は、既婚、未婚を問わない表記として1950年代に使用され始め、その後1970年代に男性を表記するMr.と対置する位置付けとして女性運動によって推奨されるようになる。
No. は、ラテン語のnumeroの略語である。ラテン語で「数」という単語はnumerusという形が辞書には載っているが、辞書に記載されている形は主格であり、意味は「数は」となる。numeroは奪格であり、「数において」くらいの意味になる。
もちろん発音は異なり、アクセント記号が付くが、フランス語ではnuméroをそのまま使っている。
詳しい説明は省くが、ラテン語では全ての名詞が、英語のI, my, meのように変化する。これは不便そうに思えるけれど、こうした方が「〜は」「〜の」「〜を」「〜に」「〜で」とかを簡単に表現でき便利であるとも言える。このようなシステムを格変化と言う。
ドイツ語やロシア語を第二外国語として学ばれた方は、この格変化の理解・暗記の悪戦苦闘の記憶が蘇るであろう。
先に考察したNo.(ナンバー)のように、実は日常生活の中でラテン語は影を潜めてはいるが主要なポジションで多く活躍している。
日常生活の言語的主要ポジションといえばやはり時システムであろう。
紀元前はB. C. と表すけれど、これは英語であり Before Christの短縮。A. D. がラテン語。
2021年という表記は「西暦」であり、これはイエス・キリストという人が生まれた年を西暦1年と数えて、今年が2021年目であることを示している。この時システムはA. D. で示される。Anno Domini(主の年において)というラテン語の略語である。
前半のanno は、anniversary(1年に1回巡ってくるもの)に含まれているものと同じ、後半のdomini はdominant(支配的な)などの英単語にその痕跡が認められる。
A. D. は、主であるイエスが生まれてからの年を表している。しかし実際には、イエスという人は西暦元年より4年くらい前に生まれていると推定されている。
現実とそれを表す言葉とのギャップがあり、今年が「西暦2021年」というのは相当に間違っていることになるが今更修復は困難であろう。一度動き出した大型船は後には戻れない。
ところで、タイやラオス、カンボジアなどに行くと、今年は2564年であると言われる。これはお釈迦様が入滅した年を仏暦1年と数える「仏暦」を採用しているからである。
計算方法は、西暦に543年を足すと仏暦になると覚えておけばよい。タイ語では、仏暦は「ポォーソォー」、西暦は「コォーソォー」という。
さて、あと少しだけ時関係のラテン語の略語を眺めてみよう。
a.m. は、ante meridiem
p. m. は、post meridiem
anteは「前」の意味で、postは「後」の意味、meridiemは「昼」の意味だから、a. m. とp. m. は、ちょうど日本語の「午前」と「午後」に相当する。
時に関係するラテン語は、月を表す語にも生きている。JulyはJulius Caesar(ユリウス・カエサル)の名に因んだものであるし、Augustはもちろん初代ローマ皇帝Augustus(アウグストゥス)でる。
ほんとうはOctoberは「8月」であり、それはoctopus(タコ)が「octo8本+pus足」であり、octave(オクターブ)が「8度音程」である ことで納得できるかも知れない。
同様にDecemberが本来「10月」であるのは、decade(10年間)やdecimal system(十進法)という英単語を想起すればよい。この辺の事情についてはHP内のブログLINGUA MANIAの初めの方にJuly for Julius
Caesarというタイトルで以前書いたことがあるので、興味のある方は覗いてみてください。
« 前のページ 次のページ »