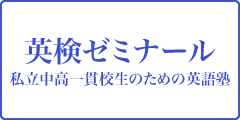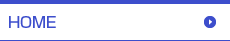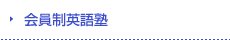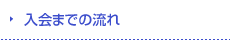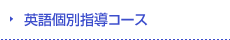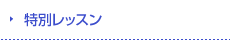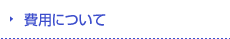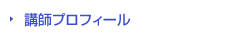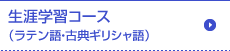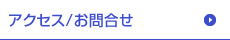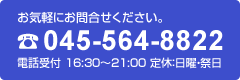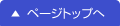Category
Archive
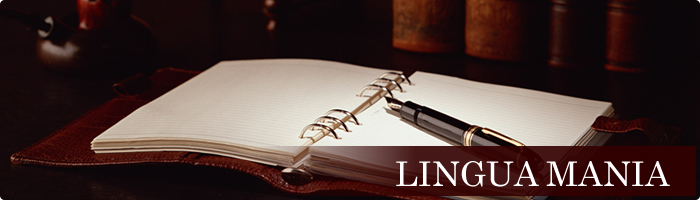
「食パン」とは何か?
「食パン」とは何か?
複合語の形成とカテゴリー分析
「食パンやメロンパンや菓子パンやあんぱんを….」と並べた時に分類の違和感を感じる人がいるかもしれない。または何も感じない人もいるであろう。ここではカテゴリーの分類に問題がある。
そもそも「食パン」とは何か、考えたことがあるであろうか?「食用のパン」であろうか?「食用の〜」の対義語は、「食用ではない〜もの」となる。
その場合、「食用の花」のように「食用ではないもの」がまずあり、そちらが基準であり、普通とは違って「食べることができる」という意味となる。
「食べることのできないパン」などはないから「食パン」を「食用のパン」という意味に分析することに間違いがあることになる。
もし食べることのできない「パン」が存在しているなら、国民全体がそれを認識しているほど語彙として浸透している必要がある。
たとえば、
A「ちょっとパンとってよ」
B「どっちのパンだよ?パンじゃ分からん」
A「パンはパンでも、あっちの食べられる方のパンだよ」
という会話が想定される。
次に「食パン」の対義語に「菓子パン」を置いてみたらどうであろう。少しの間「食」の意味は保留しておこう。
「菓子パン」とは「お菓子として食べるパン」という意味であろう。「食パン」と並べて次の連立方程式を解いてみよう。
◯菓子パン:「お菓子」として食べるパン
◯食パン:「 x 」として食べるパン
最終的に「食パン」という語の成り立ちを成立させるために「 x 」には「食」という漢字も使いたい。
さて、日常生活に目を向けてみよう。私たちが「食べる」のは一日3回の「主食」と、ちょっとつまむ「お菓子」というビジョンが浮かんでくる。
食べる>主食とお菓子
以上のことから、「 x 」は「主食」であり、「食パン」とは「主食として食べるパン」であることが見えてくる。
したがって、「食パン」は「菓子パン」と対立させた概念であり、「菓子パン」の下部カテゴリーに「メロンパン」と「あんぱん」が存在することになる。
この分析は間違っている可能性もあるが、言葉の語源を正確に知ることは極めて難しい。時代や国やその「言葉」を受け取る人によって「意味」が異なる。誰が解いてもぶれない数学より厄介であり、それゆえに言葉はより面白い。
人間と他の動物の違いは、言葉による複雑なコミュニケーション能力にあるとされている。
これからの時代は、ますます言葉の読解能力が必要となってくるであろう。なぜなら計算や分析などの数学的な事柄はAIが担当し、労働の単純作業はロボットが私たちの肩代わりをすることになるであろうから。
学校での数学が必要なくなるという意味ではない。数学は論理的思考を身につけるために行っている数字を使った言語トレーニングでもある。数学は試験のために仕方なくやるなどケチくさいことは言ってはならない。
私たち人間の方は、より人間的な事柄が求められる。言葉の効果的な使い方や人の話を忍耐強く聞く能力が必要になる。さらに一人ひとりの人間が一人ひとりのやり方で異なっているということをより繊細に認識していく必要がある。
人類全体のことを心配する必要はない。まずは自分、次に身の回りの人に優しくなろう。次には町の人みんなに。
✴︎日吉に「食パン」専門店が出来ました。その名は「ワンハンドレッドベーカリー」です。おいしいです。普通部通り
« 前のページ 次のページ »