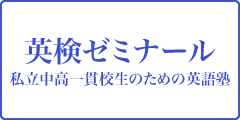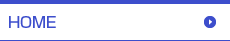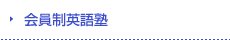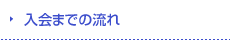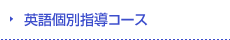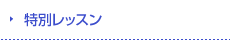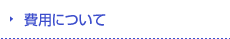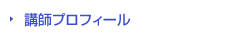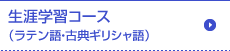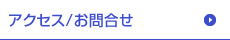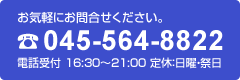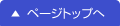Category
Archive
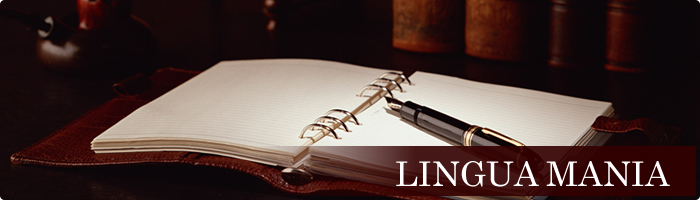
語学学習の目的とcarpe diem
語学学習の目的とcarpe diem
呼吸というものが「吸う」と「吐く」から成り立っているように、読書というものは「読む」と「書く」で成り立っているように思える。同様に会話は、「聞く」と「話す」で構成されている。
「読む・書く」と「話す・聞く」は何が違うかと言えば、前者が1人の沈黙の行為であるのに対して、後者が2人の発話行為である。
したがって「読む・書く」と「話す・聞く」の2つのペアはかなり異なった行為であり、たとえば書くことが得意な作家が話すことが得意とはならない。
明治時代以降の私たち日本での語学教育は専ら「読む」ことに焦点が当てられてきた。文明開花の名の下に優れた西洋の文化を取り入れる必要があったのだろう。現在まで語学教育の基礎はずっとここに置かれている。
漢文や古文、ラテン語、古典ギリシャ語、ヘブライ語、アッカド語などの学習は「読む」が中心で然るべきだ。なぜなら「漢文」で会話する人はいないからだ。
ところが、私たちの日常語である日本語や英語などの現代語は、言語それ自体が内包する神秘性の他に、日々使用する道具という一面がある。ナイフやホーク、箸と同様に使用される必要がある。
語学学習の目的は、人それぞれであり、さらに言えば目的などなくてもよい。学習のプロセスそれ自体を楽しめれば本当はそれでよい。
世の中は結果至上主義が幅を利かせているので、プロセスの大切さを理解してもらうことは大変なのだ。誰もが結果ばかりを追っている。
しかしながら、一人の人間のスタートが誕生だとするなら、その人間の結果は死ということになる。結果ばかりを大切がる人は、人間の誕生から死までのプロセスをすっ飛ばして死にばかり目を向けていることになる。それがいかにアホなことかは誰の目にも明白であろう。
語学学習という一括りの言葉は存在するけれど、自分とその言語の関係性にもう少しピントを合わせ、自分がどうしたいのかという問いかけが必要でもある。
もちろん試験のため、という理由でも問題ないけれど、プロセスを楽しむことができれば更に良い。同じことが受験などにも言える。
合格さえすればそれで良いと思うから不正が蔓延る。金さえ儲かれば良いと思うから詐欺が横行する。全てプロセスの大切さが蔑ろにされている。
私たちは毎日毎日、子供たちにマイナスの言葉をぶつけていないだろうか?毎日毎日。「勉強しないと偏差値の高い学校に入れないぞ!」
こんな小さなマウント合戦にこだわっているのは一体誰なのか?本当に子供たちの幸せを思った優しい気持ち?それとも我々の貪欲なエゴ?
その目標達成のために毎日(プロセス)を犠牲にしていないだろうか?親も子も。もしかしたら1日の大半、嫌なことを言って過ごしていないだろうか?
人間は人に言われた言葉は忘れるかもしれないけど、それを言われた時の感情は決して忘れないものだ。マイナスの感情はマグマのように心の底でぐらぐら煮えたぎり噴出の時を待っている。
できることから始めよう。優しい言葉を探そう。気持ち良い言葉を使ってみよう。一日いちにちを大切に丁寧に過ごそう。これがラテン語のcarpe diem の意味である。「今という時を大切にせよ」
« 前のページ 次のページ »