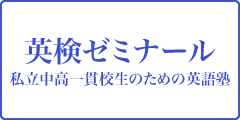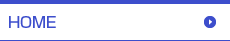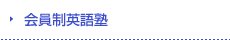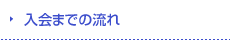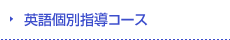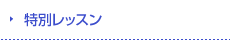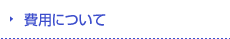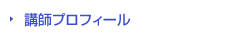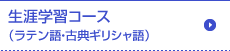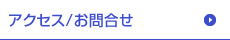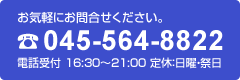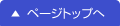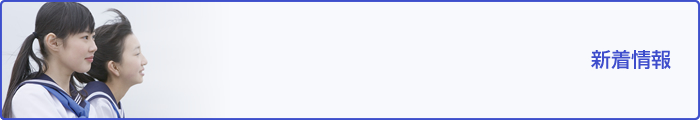
お知らせ(会員限定)
保護者面談のお知らせ etc
保護者面談
一年に2回(冬と夏)に教室にて保護者面談があります。全て予約制になります。
面談は、お一人様約10〜15分程度になります。
希望日とだいたいの希望時間をメールにてお伝えください。予約が取れ次第、返信させていただきます。
日程の合わない方は、ご相談ください。電話面談も可。
よろしくお願い申し上げます。
※マスク又はフェイスシールド着用になります。
◯日程
12/12(土)、12/13(日)、12/14(月)
◯時間帯
土日12:00〜18:00
月曜日12:00〜16:00
◯予約例(メールにて)
「12/12(土)の12:00-15:00くらいの間でお願いします。」
→「12/12(土)13:00でお取りできました。」
お知らせ(会員限定)
お知らせ(英検二次試験直前レッスン)
◯英検二次試験直前プライベートレッスン
◯11/7(土)、11/14(土)
◯15:00-20:00の時間の内お一人様約25分。
◯対象:英検一次合格者、
又は11月の英検S-CBT受験者(3級〜準1級)
◯メールにて、希望日と希望時間帯を記入の上、対象者(必要な方)はお申込みください。
◯現在、教室はお休み中ですが、メールを受け付けております。
※通常、教室のお休みの期間はメール受付を行なっておりません。
よろしくお願いします
お知らせ(会員限定)
特別レッスン「英検二次試験対策&発音レッスン(無料) 」
「発音レッスン(英検二次試験対策を含む)」
◯一人25分ですので、遊びや部活に行く前に、手ぶらで来ても大丈夫です。
◯語学で最も大切なのが音声です。
自分で発声できない音は聞き取れません。英語の音と英語のリズムを身につけましょう。音楽と同じように練習しましょう。
※特別レッスン(プライベートレッスン)の場合には、予約時間ちょうどにお越しください。ご協力お願い申し上げます。
◯対象:希望者(申込順締切)
◎発音プライベートレッスン(以下の日程・時間帯で一人1回約25分、無料)
◯日程
10/24(土)15:00〜20:00
→メール予約例)
「16:00以降を希望します」
→ 返信例) 「10/24(土)16:30-16:55で予約が取れました」
注意) あまりに細かい予約時間の指定は、できません。予めご了承ください。
※こちらかららの返信が1日以上ない場合にはメールトラブルの可能性があります。再度確認メールを出すか、お電話でご確認ください。
◯新入会(入塾1ヶ月以内)の人は受講必須。
○内容:発音矯正、発音の具体的方法、発音記号の読み方、英語のリズムトレーニング、教科書音読(学校英語の予習・復習・試験対策)、英検二次(英語面接)練習や英検一次試験の準備も音に焦点を当てたレッスンとして行います。
○メールにて、希望日と大体の希望時間をお知らせください(あまり細かすぎる指定はご遠慮ください)。
予約が取れ次第、返信いたします。
注意) お申し込み順締切で、受講できない場合もあります。予めご了承ください。
※特別レッスンの振替は、ありません。
※また予約後のキャンセルは、お早めにご連絡お願いいたします。キャンセル待ちの人が、そのご連絡によって受講可能になる場合があります。
※1つのメールにつき1つの要件でお願いします。
お知らせ(会員限定)
お知らせ(学校試験対策etc.)
「学校試験(10月中旬〜11月初旬にかけて中間・期末試験) 対策プライベートレッスン」
1人一回40分(無料)
◯対象:10月中旬〜11月初旬にかけて中間・期末試験を受ける人
◯次の日程の内、1人一回40分のプライベートレッスンの予約を行なってください。
※学校により試験日程にかなり、ばらつきがある為幅広く日程を取ってあります。それでも日程・時間帯の合わない方は、ご相談ください。
※お申込み順締切。
◯予約方法:希望日を選び、大体の希望時間を明記して、メールでお知らせください。予約が取れましたら返信いたします。
注意)メール申し込みをしたその日の内に返信がない場合には、メールトラブルの可能性があるので、再度メールまたはお電話にてご確認ください。
ただし9/19〜9/25は教室がお休みで、メール受付も行われておりません。
◯予約例→「9/26(土)の17:00以降でお願いします。」
→返信例「9/26(土)18:00-18:40で予約が取れました。」
◯以下、学校試験対策の日程
ご都合のよろしい日程と時間帯内で、大体のご希望時間をお選びください。1人一回40分。
9/26(土)15:00-21:00
9/27(日)12:00-20:00
10/3(土) 15:00-21:00
10/4(日) 12:00-20:00
10/10(土) 15:00-21:00
10/11(日) 12:00-20:00
10/17(土) 15:00-21:00
10/18(日) 12:00-20:00
10/24(土) 15:00-21:00
10/25(日) 12:00-20:00
————————————-
◯会費のお振込みは、
翌月分を毎月17日〜27日になっております。この期間を過ぎる予定の方は必ずご連絡ください。
ご協力お願いいたします。
◯9/19(土)〜9/25(金)は、教室がお休みになります。この期間分の振替はありませんので、予めご了承ください。
無料体験レッスン
無料体験レッスンのお電話でのお申し込みは、平日16:00~16:20に
受け付けております。
会費等の詳細は、全てこのホームページ内に記載されております。
お電話の前にHP全体をざっとお読みいただけると助かります。
ご協力お願いいたします。